7. 第3回公判(弁護側反対尋問)
|
|
ことりの傍聴メモ
|
| 第3回公判は2002年9月9日(月)午後1時30分より,東京地方裁判所第528号法廷にて。裁判官は中谷雄二郎(裁判長),杉山慎治,田岡薫征の3名。日本医科大の有馬 保正医師、吉田
寛医師が証人として出廷。
弁護側は,佐藤病院での手術が正常でなかったこと(誤った部位を切断したこと,結紮など適切な処置がなされていなかったこと,下大静脈にも損傷を与えたこと,など)自体については否定のしようがないため,「それらは直接の死因ではなかった」と主張する戦術である。
|
| 1.証人 有馬 保生 |
| 1) (検察側からの追加質問)死亡の届出について |
被害者の死亡は平成13年(2001年)2月9日16時40分。
医療ミスの可能性があるということであったので,遺族(谷原氏の父上)から遺体解剖についての了承をもらい,さらに日医大の法医学の専門家に相談したところ,まず警察へ届出を行うことを勧められたため,19時頃に駒込署(日医大病院の所在地管轄署)に電話で連絡。その後佐藤病院の所在地を管轄する尾久署から警察官が日医大病院に来て聴取を行った。
|
| 2) (以下,弁護側の反対尋問)2000年12月29日の再手術(通算2回目)のもよう |
胆のうは切除されており,総胆管が結紮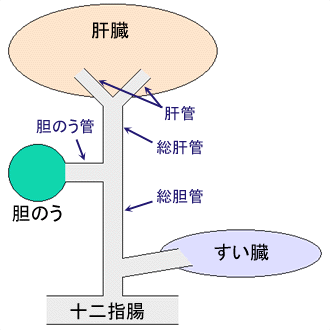 されていた。通常は胆のう管を結紮して切断し,フリーになった胆のうを摘出するのであるから,総肝管と総胆管は手術後も(従来通り)1本につながっているべきである。 されていた。通常は胆のう管を結紮して切断し,フリーになった胆のうを摘出するのであるから,総肝管と総胆管は手術後も(従来通り)1本につながっているべきである。
胆のうを引っ張りすぎて,胆のう管に続いて総胆管が引っ張られてきて1本の管のように見えたために,胆のう管と間違えて総胆管を切断してしまう・・
という失敗例があることが,専門書に記載されている。
総肝管が切断されていることについては,それが切りっ放しで結紮されていないことから,(被告人は)切断したことを認識していなかったのではないかと思われる。切りっ放しのまま放置することは,常識的にも考えられない。
肝臓から十二指腸までの領域は(一般的には右図のようになっているが),各管の長さや,つながり具合などには個人差も大きく,イレギュラーな状態になっていることも多い。また本件の場合,炎症が強く組織が硬化・ゆ着していて,各管が近接していたものと思われる。従って手術にあたっては,誤認による失敗を避けるため細心の注意をはらわなければならなかったはずである。
弁護人は「もし被告人が誤って切断したのであれば,管内の胆汁が多量に流出するから,すぐに気づくはずではないか(従って,誤って総胆管を切断したことに気づかなかったのは当然ではないか)」と指摘した。しかし,ハーモニック・スカルペル(超音波凝固切開装置)を用いて切断した場合,(傷口はすぐに凝固するので)ほとんど胆汁が漏れ出さないこともありうる。
通常は胆のう管だけを切断するのだから,それが結紮されていれば胆汁が漏れることはなく,本件のようにドレーン(体液を体外へ導く管)から胆汁が出るといったことはありえない。弁護側は「肝臓から,ゆ着した胆のうをはがす際に,肝臓本体に傷がつき,そこから胆汁が漏れたのではないか(従って,ドレーンから胆汁が流出したからといって,誤って総胆管を切断したことに気づかなかったのは当然ではないか)」と指摘した。しかし,再手術の際に見た限りでは胆のうをはがした面はきれいであり,肝臓本体の傷から胆汁が漏れたとは考えにくい。
|
| 3)
ドレーンから胆汁が漏れていた事実について |
手術後,胆汁が漏れること(胆汁漏)があった場合,それがどの程度であれば異常と判断すべきであるか(被告人は2000年12月21日の手術当日から胆汁漏を認めながら,27日にようやく精密検査を行う決定をするまで,経過を観察するだけであった。これが正当であったかどうか)。
異常かどうかの判断は,漏れた胆汁の量はもちろんであるが,患者の状態をみて判断するべきであり,それには経験を必要とする。本件の場合では,胆汁の漏出量も多く,発熱もあって感染が疑われる。さらに佐藤病院では鎮痛剤が(かなり大量に)処方されていたことから,痛みも強かったものと思われる。従って「経過観察」という判断は無謀であり,早期に精密検査を行うべきだったと考えられる。
弁護側は12月28日に日医大病院に転院した際に撮影した腹腔内CT写真を証人に示し,大量の胆汁の貯留はみられないことを確認させた。これは「実際には胆汁漏は軽微であった(従って,経過観察にとどめた被告人の行為は正当であった)」と主張するためである。しかし証人は,CT写真は一つの断面に過ぎず,その1枚だけで胆汁漏の程度を判断することは無理がある,と応えた。
|
| 4) 死因について |
(A)
胆汁性腹膜炎(アルカリ性の消化液である胆汁が腹腔内に漏れたことによって炎症が発生する)
→ 臓器,腹膜のゆ着 → 腸閉塞 → 腸の内容物の滞留
→ 腐敗して毒素が血液中に回って敗血症
(B)
全身的な免疫力の低下によって感染症にかかり,「臓器障害の前段階」というべき状態となった
(C)
呼吸障害,腎障害を起こし,血液循環が不安定となった
以上の要因によるものと考えられる。
2001年1月24日の再手術(通算3回目)は,腸閉塞(イレウス)の治療のためであった。弁護側は「直接の死因は,日医大病院における再手術にある」という観点から,以下のような質問を行った。
2001年1月24日の再手術(通算3回目)の記録によると,「まひ性のイレウス」がみられ,「機能性イレウス」ではなかった。後者ならば物理的に腸の通りが悪くなっているのだから直ちに手術するのが当然であるが,前者の場合手術は避けるべきではなかったのか。
これに対して証人は次のように述べる。
イレウスの発症は確かに1月初旬と考えられる。2000年12月29日の再手術(通算2回目)の時点では,(腸に)浮腫がみられ拡張気味ではあったが,イレウスとの認識はなかった。手術中から既に頻脈,血圧上昇,循環量減少があり,感染による敗血症の前段階と考えられた。12月31日の検査では腸管運動がマイナス(動きがない),1月2日には肝機能こそ改善したものの腸管からの吸収がなく,腎不全,肺水腫による呼吸不全が始まった。以上から物理的な機能性イレウスの可能性があり,手術が必要と判断した。まひ性のイレウスであると判明していれば手術は行わなかっただろう。結果的には,腸が折れ曲がったりした部分はなかった。むしろ感染症の悪化が激しかったため,細菌の「巣」になっていると思われる下大静脈の血栓に対して,拡散を防ぐフィルターを入れる処置を行った。
バイコマイシンなどの抗生剤の投与によっても感染症が改善しなかった理由として,下大静脈の血栓(佐藤病院で傷つけたことが原因で生じたと思われる)が細菌の「巣」となり,ここで繁殖して全身に回っていることが考えられた。血栓による血行障害と細菌感染によって浮腫(むくみ)が生じ,腹腔内全体が癒着して硬くなり,腸の通りも悪くなって,腸閉塞の状態になっていたものと思われる。
|
|
5) 輸液について
|
弁護側は,日医大病院での看護日誌をもとに,2000年12月29日の再手術(通算2回目)中からその後の数日間にわたって毎日数千ccの輸液を行っており,これに対して体外に排出された量が少ないことを指摘した。すなわち体に水分が大量に入っている。そこで「輸液の量が多すぎ,これによって腎不全,肺水腫が誘発され,直接の死因となった」という観点から質問を行った。
証人は,これは手術前から脱水状態であったためで,必要な輸液であったと考えている。
|
|
6) その他
|
感染症は最後まで改善がみられず,抗生剤の投与も効果がなかった。血栓の拡散を防ぐために入れたフィルターに細菌が付着し,かえって感染の元となっている可能性があったので,これを除去して検査したところ,真菌(カビ類など)が検出された。
|
|
2.証人 吉田 寛
|
| 1) (以下,弁護側の反対尋問)2000年12月28日転院直後の状態について |
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影撮影
-
専用の内視鏡を口から十二指腸まで挿入し,総胆管が十二指腸へ出ている口から逆に造影剤を送り込んでX線撮影する)によって,総胆管が途絶していることが判明。途絶部分が結紮されているのか切断されたままなのかは,検査の時点では不明だったが,これが原因で胆汁が漏出しているであろうことは認識できた。
検査の結果,可能な対応としては肝管空腸吻合術(空腸を一旦切断して,その一方を肝臓の近くで肝管とつなぎ,そこにさらにもう一方をつなぐ)がベストであると考えられた。胆汁の漏出を止め,消化管内に正しく流すことが重要だからである。
|
| 2) 2000年12月29日の再手術(通算2回目)のもよう |
もし実際に開腹してみて状況が悪い(癒着や浮腫などが激しくて縫い合わせることができない程である)場合は,次善の策として手術を2回に分け,一旦閉腹して改善を待ち,他日改めて吻合術を行うことも考えられる。しかし本件の場合はそれ程の状況ではなかったので,1回の手術で吻合を行った。
腹腔内の洗浄は十分に行い,肝管空腸吻合術も成功した。従って手術の目的は達成された。
しかし,予期せぬ結果として,術後に強い癒着が起こった。
|
| 3) 輸液の影響 |
弁護側は再び「輸液の量が多すぎ,これによって腎不全,肺水腫が誘発され,直接の死因となったのではないか」という観点から質問を行った。証人はこれに対し,
| 感染症が悪化 |
→ |
浮腫(むくみ) |
→ |
脱水状態 |
→ |
腎不全 |
| → |
バンコマイシン投与 |
→ |
副作用としての腎機能低下 |
→ |
脱水状態に対処するためには大量の輸液を行う必要がある。輸液が奏効し腎機能が回復すると,リフィリング(回復期に細胞内に蓄えられていた水分が急激に循環系内に戻る現象)が起こり,CVP(中心静脈圧)値が上昇する。すると心不全や呼吸不全の危険が出てくるので,人工呼吸器によって対処する。以上は標準的な処置であり,大量の輸液は異常ではない,と説明した。
|
| 4) MRSAについて |
転院時に発熱があり,感染が疑われたためカテーテルを外したところ,カテーテルから菌が検出された。2001年1月5日に明確にMRSAが検出された。
再手術で下大静脈の血栓がみられ,佐藤病院での最初の手術で下大静脈を損傷していたことがわかった(佐藤病院からの引き継ぎではこの点が隠蔽されていた)。この血栓が感染の巣になった可能性がある。
佐藤病院では循環不全治療薬(昇圧剤),鎮痛剤を処方していた。とくに鎮痛剤は手術後1週間にわたって大量に投与しているが,これは当然痛みがあったからこそ行われたのであり,従ってその時点で既に感染があったことを示している。
|
| 5) 2000年1月29日の再手術(通算3回目)の目的 |
イレウス(腸閉塞)の解消。もしそれが無理ならば,腸内に栄養導入を行う。実際にはイレウスは解消できた。
|
| 6) (裁判官からの質問)下大静脈の損傷について |
下大静脈を損傷した場合,当然その前面にある腸管も傷つけられたと考えるのが妥当である。
|
| ←前へ ★ 目次へ戻る ★
次へ→ |
 Last Updated:
11 October 2002 Last Updated:
11 October 2002 |
|
mailto:<webmaster@tanihara-sei.net>
|
 Last Updated:
11 October 2002
Last Updated:
11 October 2002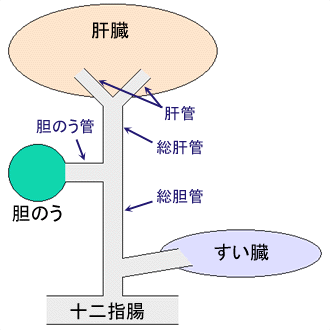 されていた。通常は胆のう管を結紮して切断し,フリーになった胆のうを摘出するのであるから,総肝管と総胆管は手術後も(従来通り)1本につながっているべきである。
されていた。通常は胆のう管を結紮して切断し,フリーになった胆のうを摘出するのであるから,総肝管と総胆管は手術後も(従来通り)1本につながっているべきである。